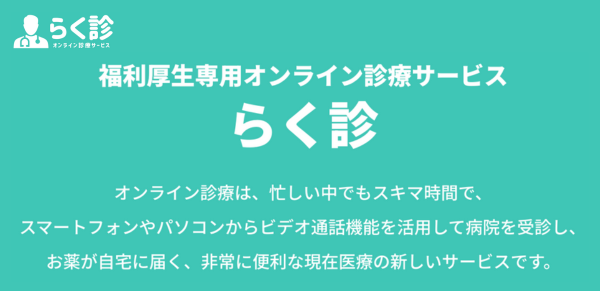朝目覚めたあと、ついもう一度布団に潜り込んでしまう「二度寝」。怠けているだけと思われがちですが、実は脳や体に意外な良い効果があります。
この記事では、二度寝がもたらす良い効果、好ましくない効果、そして二度寝を活用するコツなど科学的な知見をもとにお伝えします。正しい知識で、二度寝をより心地良く楽しみましょう。
そもそも二度寝とは?
二度寝は怠惰に思えるかもですが、実は良くも悪くも脳や体にさまざまな影響を与えます。ここでは、まず二度寝の定義と、そもそもなぜ二度寝をしてしまうのかをお伝えします。

二度寝の定義と一般的なイメージ
二度寝とは、一度目覚めたあとに再び眠りに入ることを指し、日常的にもよく見られる自然な行動です。この行動は、通常の連続した睡眠とは違い、睡眠のサイクルを一時中断した後にもう一度再開する形になるため、脳と体のリズムに特別な影響を与えます。
厚生労働省やアメリカ睡眠医学会(AASM)の見解では、二度寝は「中途覚醒後の再睡眠」と定義され、リラックス効果が得られる場合もありますが、タイミングや時間を間違えると逆効果になることも指摘されています。
・二度寝=目覚めた後に再入眠する行為
・リラックス効果をもたらすことがある
・長時間の二度寝は体内リズムを乱すことも……?
なぜ二度寝してしまうのか?
二度寝が起こる理由は、睡眠の質や量の不足、体内時計の乱れ、そして心理的な安心感への欲求にあります。睡眠不足や浅い眠りが続くと、脳は「まだ休みたい」と再度睡眠を促します。また、ストレスや疲労がたまっていると、少しでも布団に留まることで安心感を得ようとする心理も働きます。
日本睡眠学会やスタンフォード大学の研究によると、体内時計のリズムがずれると、覚醒ホルモン(コルチゾール)の分泌が遅れ、起床後も眠気が残りやすくなるとされています。これが二度寝の大きな引き金になります。
・睡眠不足や質の低下が二度寝を引き起こす
・体内時計の乱れが起床困難を招く
・ストレスや不安を和らげるために二度寝することもある
それでは次章は本題にあたる二度寝の効果についてお伝えします。
二度寝の良い効果とは? 主にストレスの軽減と脳機能の向上
二度寝は適切に取り入れれば、ストレス解消や脳のパフォーマンス向上に役立つことが、最新の研究でも示されています。ここでは、二度寝がもたらす良い効果を掘り下げます。

リラックスによるストレス軽減効果
適度な二度寝は、一度目覚めた後に再び眠りに入ることで、副交感神経が優位になり、身体がリラックスモードへと切り替わるため、ストレスを軽減し、心身を深くリラックスさせる働きがあります。
スタンフォード大学睡眠研究所の報告によれば、短い二度寝を取ることで、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が抑えられ、心身の回復に役立つことがわかっています。また、厚生労働省の健康資料でも、短時間睡眠が自律神経の調整に好影響を与えるとされています。
・副交感神経を活性化して心身をリラックスさせる
・コルチゾール分泌を抑え、ストレス負荷を低減
・気持ちの安定やリフレッシュに効果が期待できる
脳の情報整理機能と記憶力アップ
睡眠中、特に浅い眠りの段階では、脳がその日得た情報を整理・再構成する働きをしており、二度寝がこのプロセスを後押しすることから、二度寝を活用することで、脳内の情報整理が進み、記憶力向上につながる可能性があります。
ハーバード大学医学部の研究では、短い昼寝や二度寝を取ったグループが、そうでないグループよりも記憶テストの成績が良好だったことが示されています。また、日本睡眠学会も、短時間の二度寝が記憶の定着を助ける可能性があると紹介しています。
・二度寝によって脳の情報整理が進む
・記憶の固定化と呼び出しやすさが高まる
・学習効率やクリエイティブな発想をサポートする
二度寝による好ましくない効果
二度寝には前述した良い面もありますが、同時に気をつけたいデメリットも存在します。特に、サーカディアンリズムの乱れや起床時のだるさは、日常生活や仕事においての生産性に好ましくない影響が懸念されます。ここでは、二度寝によるデメリットをお伝えします。

サーカディアンリズム(概日リズム)の乱れ
サーカディアンリズム(概日リズム)とは、地球の自転に合わせた約24時間の周期で起こる精神面と身体面の状態の規則的な変化のことです。サーカディアンリズムは朝の光、一定の起床時間、食事のタイミングなどによって維持されていますが、二度寝で起床時間がずれるとリズムが乱れ、夜の睡眠の質にも影響を与えやすくなります。
国立精神・神経医療研究センターの発表によれば、毎日の一定した起床時間が体内時計の安定に不可欠であり、二度寝を頻繁に繰り返すと社会的時差ボケにつながる可能性があるとされています。
・起床時間のズレが体内リズムを狂わせる
・夜の寝つきが悪くなる可能性がある
・慢性的な睡眠不足や体調不良につながる可能性がある
起床時のだるさ・眠気の増加
目覚めた後に再び寝てしまうと、深いノンレム睡眠に入りやすくなり、その状態から無理に目覚めることで脳が完全に覚醒できず、強い倦怠感を残してしまうため、二度寝をすると起床時のだるさや眠気が強まる傾向があります。
『Sleep Medicine Reviews』の研究では、ノンレム睡眠中の強制的な覚醒によって「睡眠慣性」と呼ばれる現象が起こり、判断力や集中力の低下を引き起こすと報告されています。
・再度深い睡眠に入ると目覚めが悪くなる
・起床後も眠気や頭の重さを感じやすい
・日中のパフォーマンス低下を招く可能性がある
二度寝を活用するには? 好ましいのは20~30分以内

好ましい二度寝で心身に好影響を与えるためには、20~30分以内の短時間に留めましょう。短時間の睡眠であれば脳と体が軽く休まり、深い眠りに入る前にすっきりと起きやすくなります。
スタンフォード大学の研究では、20~30分の仮眠が認知機能や集中力向上に効果的であり、逆に長時間眠ると睡眠慣性によるだるさが生じると報告されています。
・二度寝は20~30分を目安にする
・長く寝すぎないようアラームをセットする
目覚めをスムーズにする工夫

二度寝から気持ちよく目覚めるには、朝の光と軽い身体刺激をうまく活用します。自然光を浴びることで体内時計がリセットされ、脳が覚醒しやすくなります。また、軽いストレッチや冷水で顔を洗うことによって交感神経が刺激され、目覚めが促進されます。
米国睡眠財団によると、朝の光は体内リズムを整える重要な要素であり、ストレッチなど軽い運動は覚醒を助けると推奨されています。
・カーテンを開けて自然光を取り込む
・起きたら軽く体を動かして血流を促す
・冷たい水で顔を洗ってリフレッシュする
まとめ:二度寝の効果

・二度寝とは、一度目覚めたあとに再入眠する自然な行動であり、リラックス効果を得られる反面、タイミングを誤ると体内リズムを乱すリスクもあります。
・二度寝が起こる主な理由は、睡眠不足や体内時計の乱れ、そしてストレスや不安による心理的な安心感への欲求が背景にあるとされています。
・適切な二度寝は、副交感神経を優位にして心身をリラックスさせ、コルチゾール分泌を抑えることでストレス軽減や気持ちの安定に役立ちます。
・脳の情報整理や記憶の固定化にも二度寝は有効であり、短時間であれば学習効率向上や新しい発想力をサポートする可能性が高まります。
・健康的な二度寝には20〜30分以内の短時間睡眠と、起床後の光・ストレッチによる覚醒リズム作りが効果的であることが、各種研究から示されています。