「なんとなく疲れが取れない」「眠ってもスッキリしない」「イライラしやすくなった気がする」というような感覚は、自律神経の乱れ が関係している可能性があります。
自律神経は、体調・気分・睡眠のリズムを支える重要な神経です。ここでは自律神経が乱れる主な原因や不調としてあらわれるサイン、そして今日から実践できる整え方などをお伝えします。
そもそも自律神経の乱れとは?サクッとおさらい
自律神経は体のあらゆる働きを自動で調整する存在で、ここでは簡潔におさらいしましょう。
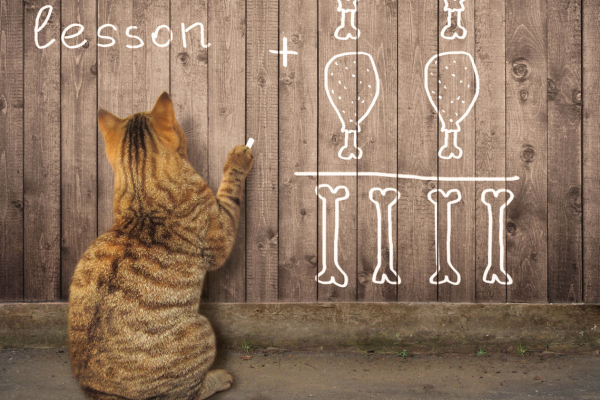
自律神経の役割とバランスの仕組み
自律神経は意識しなくても体の調子を整えてくれている神経で、呼吸や心拍、血圧、体温、内臓の働きなど、日常のあらゆる生命活動を24時間サポートしています。
・呼吸や心拍、消化といった無意識の働きの調整
・外の環境や状況に応じて体を適応させる仕組みの維持
・朝と夜のリズム(体内時計)を整える機能の補助
このバランスが乱れると、頭痛・倦怠感・不眠・胃腸の不調など、いわゆる原因がはっきりしない体調不良が起こりやすくなるとされています。
交感神経と副交感神経の関係
自律神経は交感神経と副交感神経の2つで構成されています。交感神経は活動モード、副交感神経は休息モードであり、この2つがバランスよく切り替わることで、体の調子は安定します。
それぞれの働きは、
交感神経(アクセル):心拍を速め、血圧を上げて体を戦闘モードにする
副交感神経(ブレーキ):心拍を落ち着かせ、胃腸の働きを整える回復モードに導く
日中は交感神経が、夜やリラックス時は副交感神経が優位になるのが理想です。ですが、ストレスや生活習慣の乱れが続くと、交感神経が優位なままになりやすくなります。
この状態が続くことで、自律神経失調と呼ばれるような慢性的な不調につながるとされています。なので、日々の生活の積み重ねが、自律神経のバランスを左右しているとも言えます。
自律神経が乱れる主な5つの原因
特別な病気があるわけでもないのに、疲れが取れない・眠れないと感じるなら、まずは日常の中にある原因を見直してみることが有効です。ここでは、代表的な5つの要因についてご紹介します。

① ストレスによる影響
自律神経が乱れる原因として、まず挙げられるのがストレスです。ストレスを感じると、身体は緊張状態になり交感神経が過剰に働いてしまい、これが続くと、副交感神経への切り替えが上手く機能しなくなります。
懸念される場面の具体例
・職場や家庭での人間関係に悩んでいる
・常にプレッシャーを感じながら過ごしている
・慢性的な体の不調や疲れが続いている
長期に及ぶストレスは、自律神経の働きを鈍らせる要因になることがあります。
② 生活リズムの乱れ
睡眠不足や夜更かしといった不規則な生活習慣も、自律神経のバランスを崩す大きな要因です。特に睡眠不足や夜型の生活が続くと、交感神経と副交感神経の切り替えが乱れ、疲労感やだるさが取れにくくなります。
当てはまりやすい習慣の具体例
・毎日寝る時間と起きる時間がバラバラ
・就寝直前までスマホやPCを触っている
・朝起きてもスッキリしない日が多い
生活リズムの乱れが交感神経の過活動を招くとされており、それが自律神経失調のきっかけになるとも言われています。
③ ホルモンバランスの変化
特に女性はホルモンの変動によって、自律神経が乱れやすくなります。月経周期、更年期、妊娠・出産などによるホルモンの揺らぎが、心身のバランスに大きく影響します。
不調が現れやすいタイミング
・月経前に気分が落ち込んだり、イライラする
・更年期に入ってから不眠や動悸が気になる
・出産後、心身のバランスが戻らない
女性ホルモンの変動は自律神経の中枢にも作用するため、より影響が出やすくなります。
④ 運動不足・過労・栄養不良
運動不足や過労、栄養の偏りが重なると、交感神経が働きすぎる状態になり、身体のリズムが崩れてしまいます。気をつけたい習慣としては、
・一日中座りっぱなしで体を動かさない
・食事の時間や内容がバラバラになっている
・疲れているのに休めない状態が続いている
上記のような生活習慣の乱れが自律神経の働きを鈍らせ、疲労やストレスの回復を遅らせる要因のひとつになります。
⑤ 気温差や湿度などの外的環境要因
環境の変化も自律神経にとっては大きなストレスであり、特に急激な気温差や湿度の変化は、体の調整機能に負担をかけ、自律神経のバランスを崩しやすくなります。
影響を受けやすい状況の具体例
・冷暖房の効いた室内と外気との温度差が大きい
・梅雨時の湿度や、季節の変わり目に体調を崩しやすい
・台風や低気圧で頭痛やだるさを感じる
気候変化による影響が、自律神経の調整機能を揺さぶるとされています。

自律神経の乱れによって起こる不調3選
ここでは、自律神経のバランスが崩れたときに起こりやすい代表的な不調を3つのカテゴリに分けて、ご紹介します。

① 頭痛・肩こり・だるさ
交感神経が働きすぎると筋肉が緊張して血流が悪くなり、頭痛や肩こりが慢性化しやすくなるため、自律神経の乱れは、体のあちこちになんとなく不調を引き起こします。
現れやすい症状の具体例
・慢性的な緊張型の頭痛がある
・肩や首まわりがガチガチにこる
・ぐっすり寝たはずなのに疲れが取れない
自律神経が崩れることで、明確な病気は無いのに体がツラいと感じるケースが多いとされています。
イライラ・不安感(メンタルへの影響)
脳の中では自律神経と感情をコントロールする神経がつながっていてバランスが崩れるとイライラしやすくなったり、不安を感じやすくなったりするため、気分の不安定に自律神経が関係している場合があります。
・小さなことに過敏に反応してしまう
・どことなく気持ちが落ち着かない
・理由もなくモヤモヤや不安が出てくる
・やる気が出ず、気分が沈みがちになる
自律神経が乱れるからの、感情の起伏が大きくなりメンタルのバランスを崩しやすくなります。ストレスがかかる環境に長く身を置くことで、悪循環に陥るケースも少なく無いです。
睡眠の質低下による影響
自律神経のリズムが崩れると、朝起きられない、日中に眠いといった状態になりがちです。
よくある傾向の具体例
・アラームを何度止めても起きられない
・午前中は集中力が上がらず、ぼーっとする
・昼過ぎになると強い眠気に襲われる
・朝からずっと体が重く、やる気が出ない
起立性調節障害に関する情報でも、活動と休息のリズムにおいての障害は大人にも多く見られるとされていて、慢性的に続くと生活全体に支障が出てしまいます。
自律神経のバランスを整える方法
ここでは、すぐに取り入れやすい自律神経の乱れの改善方法をご紹介します。生活の中でできることから少しずつ整えていくことで、心と体のバランスは必ず取り戻せます。

食事・運動・入浴などの生活改善
まず見直したいのが、毎日の生活リズムです。乱れた自律神経は、バランスのいい食事や軽い運動、リラックスできる入浴などの整える習慣で回復を促すことができます。例えば、
食事:ビタミンB群やマグネシウム、発酵食品などを意識して摂る
運動:ウォーキングや軽いストレッチなど無理のない有酸素運動を習慣に
入浴:38〜40℃のぬるめのお湯に10分ほどゆっくり浸かる
生活習慣の改善が交感神経と副交感神経の切り替えをスムーズにする効果があるとされています。意外とシンプルなことの積み重ねが、体を整える土台になります。
呼吸法・マインドフルネス・瞑想などのセルフケア
心の緊張をほぐすことも、自律神経を整えるにはとても大切です。特に呼吸を意識したり、頭の中を静かにする時間を持つことで、副交感神経が優位になり、体がリラックスしやすくなります。
腹式呼吸:4秒かけて吸い、8秒かけてゆっくり吐くリズムで呼吸する
マインドフルネス:今この瞬間の体の感覚に意識を向けてみる
瞑想:1日5〜10分、静かに座って呼吸だけに集中する時間を持つ
上記の方法は過剰に働きがちな交感神経を鎮めてくれる効果があり、継続することで心身の安定につながるとされています。
睡眠環境の見直しが重要な理由
夜間にしっかりと副交感神経が働くことで体も心もキチンと回復する。そのためには、どのように眠るかだけでなく、どのような環境で眠るかも見直しておきたいポイントです。
効果的な工夫
・寝室の照明を暖色系のやわらかい光にする
・寝る前1時間はスマホやパソコンから離れる
・枕やマットレスを自分の体に合ったものに変えてみる
睡眠環境の改善が自律神経のリズムを整える上で有効なので、眠る時間=自律神経を整える時間という視点を持ちましょう。
整体師もすすめる『寝ながら自律神経が整う枕』の効果とは
寝ても疲れが取れない、朝の目覚めがすっきりしない、そのような悩みがあるなら、眠り方に加えて寝具も見直すことで、より改善しやすくなります。実は、自律神経の乱れの改善には、枕選びが深く関係していて、最近注目されているのがキュレアの「THE MAKURA」です。
整体師47人が証明した『寝るだけ整体』の効果
THE MAKURAは、整体師47人がその効果を認めた 寝るだけの整体枕 です。実施された比較検証では、全国の整体師47人が集まりTHE MAKURAの原型である「けんこう枕」との整体対決を行いました。
その結果は枕側の47勝。つまり、全員がその整体効果を実感したという結果でした。施術者自身が「施術と同じ、もしくはそれ以上の体感がある」と認めた信頼感のある枕と言えます。
効果の理由は『頸椎の負担を軽減し自律神経を整える構造』
THE MAKURAの内部は3つのゾーン頭・首・肩に分かれていて、それぞれ独立して支える構造です。その中でも特に、頸椎への負担を限りなくゼロに近づける工夫がされています。
この工夫により、
① 脳からの「回復の信号」が全身に行き渡るようになる
② 首が自然な位置に戻ることで、自律神経が切り替わりやすくなる
③ 朝のだるさや疲労感が軽くなる
こうした効果は枕の仕様だけでなく、利用者の実感としても数多く報告されています。
他の枕との違いは?実際に使った口コミと実感
THE MAKURAの特徴は、今までの枕と全然違うという声に集約されています。見た目はシンプルですが、使ってみると明らかに何かが違うと感じる方が多く、実際の口コミには、
「朝起きたら肩がふにゃふにゃになっていて驚いた」
「事故で首が動かせなかったのに、この枕で眠れるようになった」
「枕を替えただけで、首・肩・腰の動きが軽くなった」
横向き寝の方にもフィットしやすく使い続ける内に、これがないと寝づらいと感じる方もいます。
なぜ自律神経の乱れ改善に枕が有効なのか?
自律神経は脳から背骨に沿って全身に伸びていますが、特に首周辺はその出入り口ともいえる場所であり、ここに持続的な圧や歪みがかかると、交感神経が優位になりやすく、リラックスできない状態が続いてしまいます。そのため、自律神経の中枢がある首元を、どのように支えるかが重要です。
・睡眠中に首がこわばることで、自律神経のスイッチが切り替わらない
・首の負担が副交感神経の働きを妨げ、回復力が落ちる
・頸椎が正しく支えられることで、自然とバランスが整う
THE MAKURAは、そうした自律神経の通り道に配慮した構造だからこそ、寝ながら整うという表現をしています。
まとめ:睡眠時間にこそ身体と自律神経を整える習慣を
一日の中で最も自律神経が回復する時間が、睡眠です。枕やマットレスを見直すのはもちろん、寝る前の過ごし方も含めて、整えるための休息時間に変えていくことで自然と自律神経のバランスが戻りやすくなります。例えば、
・寝る前にスマホを触るのをやめてみる
・リラックスできる音楽やアロマを取り入れる
・自分の体に合った枕を選び直してみる
こうした「寝る前1時間の習慣」が、副交感神経を優位にして、質の高い睡眠と翌日のコンディションにつながります。THE MAKURAのような寝ながら整うアイテムを活用するのも、無理なく自然な形で始められる工夫のひとつです。


