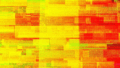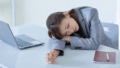「SNSを見ると置いていかれている気がして、ちょっとだけ不安になる」そのような状態になることは、FOMO(フォーモ)と呼ばれている感覚です。
FOMOとは「自分だけが何かを見逃しているかもしれない」と感じる現代特有の心理状態のことで、SNSや情報の波にさらされる日々の中で僕たちは自然と、この感覚に陥ります。
ここでは、FOMOの基本的な意味、心への影響やマーケティングでの活用例、そしてFOMOとうまく付き合うための方法などをお伝えします。

FOMOとは何か?
FOMO(フォーモ)とは 取り残されることへの不安 を意味する言葉です(Fear of Missing Outの略)。具体的には、自分がいない場所で何か面白いことが起きているかもしれないという気持ちが、落ち着かなさや不安感を生み出します。その背景には現代の情報環境があり、
・SNSを通じて、他人の行動がリアルタイムで見えるようになった
・楽しそうな投稿を見ると、自分だけ何もしていない気がしてしまう
・情報を逃すことが損失に感じられるようになった
こうしたFOMOによる感情は、自己決定理論における他者とのつながり欲求が満たされていない状態と結びつくとされています。「誰かとつながっていたい」「共通の話題についていきたい」という思いがFOMOを引き起こす要因になります。

FOMOという言葉のルーツと広まり
FOMOという言葉は、2004年にハーバード・ビジネス・スクールの学生だったパトリック・J・マクギニスが生み出した造語です。彼は学内誌『The Harbus』に掲載した記事の中で、FOMOとその関連概念「FoBO(より良い選択肢を逃すことへの恐れ)」を提起しました。
また、SNSの登場と普及により他人の行動が可視化されたことにより学生やビジネス層を中心に「今を逃すな」という感覚が共感を集め、さらにマーケティングや心理学の分野でも、FOMOは注目されるようになりました。
なお、心理学的な観点からFOMOに近い行動を分析した最初の研究者は、ダン・ハーマン(オクラホマ州立大学准教授)です。彼は1996年にFOMO的な消費者心理を指摘し、2000年に専門誌へ論文を発表しています。このように、FOMOは学術・実務の両面で関心を集めてきた概念です。
FOMOが起こる主な原因
ここでは、特にFOMOの影響が大きいSNS、情報過多、デジタル依存の3つについてお伝えします。

SNSとの関係性
FOMOが生まれる大きな要因のひとつはSNSの存在です。SNSでは、友人や知人の楽しそうな投稿がタイムラインに次々と流れてきます。それを見るたびに「自分はそこにいなかった」「何かを逃したのでは」と感じてしまいのです。というのも、SNSの特徴にあります。
・他人のリアルタイムの出来事が手に取るように見える
・楽しい瞬間や充実した生活が強調されやすい
・いいねやコメントの数で比較が生まれやすい
実際の研究によると、SNS利用がFOMOの感情と強く関連していることが示され、また別の調査では他人の投稿を見た後にネガティブな感情を抱くユーザーが多く、自分自身の生活に対して不満を感じやすくなる傾向も報告されています。
情報過多とデジタル依存の影響
スマホやSNSの普及によってFOMOはさらに強まりやすくなっています。今やニュース、通知、投稿など、1日に受け取る情報量は膨大です。それらを常に把握しようとする行動が、さらに不安や焦りを助長させてしまいます。
・絶えず更新されるコンテンツに「ついていかなければ」という心理的圧力
・すべての情報を見ておきたいという心理がストレスになる
・オフラインでいる時間が損失と感じられてしまう
このような状態は、選択を逃すことへの恐れ(regret aversion)とも関係していて、2018年の研究によると、特に若い世代では「オンラインでつながっていないと不安になる」という心理がネット依存の一因になっていることも明らかになっています。
FOMOによる具体的な心理的影響
FOMOによって、精神的なストレスや人間関係に影響を及ぼすことが分かってきています。SNSを見てモヤモヤしたり、なんとなく焦りを感じるようになったり……そのような日常の感情の裏にFOMOは潜んでいます。ここでは、FOMOによる具体的な影響についてお伝えします。
不安感とストレスからの睡眠への影響
「取り残されたくない」「自分も何かしていないと不安」といった思いが、常に心のどこかにあると、リラックスする時間すら感じにくくなってしまいます。結果、FOMOは不安やストレスを増やす要因になることが明らかになっています。そうなると、このような行動や状態が目立ちます。
・SNSやニュースを頻繁にチェックしてしまう
・スマホが手放せない感覚になる
・情報に追いつけないことへの焦燥感が強まる
こういった心理的な負担は、少し古いですが2013年の研究でも報告されていて、FOMOが睡眠の質や集中力の低下とも関係しているとされています。
SNSによる自己肯定感への影響
SNSで目にする他人の投稿と自分の現実を無意識に比較してしまうため、FOMOは人とのつながりや自分自身の価値観にも大きな影響を与えます。FOMOの影響が考えられる例としては、
・他人の楽しそうな様子を見て、自分が劣っているように感じる
・自分だけ孤立しているような気がして落ち込む
・無理にSNS上のつながりを保とうとして疲れる
研究ではSNSの利用が嫉妬や孤独感、そして自己評価の低下に影響することが報告され、FOMOが強い人ほど他人との比較が習慣化しやすく、それによって自己肯定感を失ってしまいやすいです。
FOMOから脱却する方法
FOMOを感じるたびにSNSを見たり、誰かの行動に敏感になったりして、気づけば心が疲れていた。そんな経験、僕も含めて多くの人があると思います。でも、FOMOはうまく付き合うことで少しずつ手放していけます。ここでは「JOMO」という考え方と、すぐに実践できる対処法を紹介していきます。
JOMOとの違いと概念
JOMO(ジョーモ)は、情報を見逃しても大丈夫、むしろその方が心地いいと思える、ちょっと肩の力を抜いた価値観です。そこでFOMOから抜け出す鍵は、JOMO(Joy of Missing Outの略)という考え方にあります。FOMOとJOMOの違いは対極にあり、
FOMO:他人の動きに反応して行動しがち
JOMO:自分の気持ちを優先して選択できる
FOMO:つながり続けないと不安になる
JOMO:つながっていない時間を楽しめる
JOMOは、情報社会を生きる上での心のゆとり とも言われることがあります。何でも知っていたい、参加していたい、という気持ちを一度手放すことで自分の時間を豊かに使えるようになる。JOMOには、そのような発想があります。
対策方法はデジタルデトックスの実践
FOMOを減らすには、スマホやSNSとの距離感を見直すことが効果的です。見逃したくないという気持ちを無理になくそうとするよりも、見る時間を減らす だけで心が軽くなる感覚があり、実際にやってみるとなかなかに実感できます。
対策方法の例
・スマホの通知を最小限に設定する
・食事中や会話中はスマホをしまう
・週に1日は「スマホを見ない日」をつくる
・寝る前1時間はデジタル機器に触れない
| 『デジタルデトックス』人気グッズをチェック |
 |
| Amazonでチェック |
| 楽天市場でチェック |
スマホを使わない時間を決めると、自然に自分の時間や感情に意識が向きやすなります。このような習慣がFOMOの感情を緩やかに整えてくれます。表現を変えると、その時間を自分がどのように過ごしたいか?に立ち返ることでFOMOに振り回されずに済むことになります。
FOMOを活用したマーケティング手法
「今だけ限定」「残りわずか」といった言葉に、つい反応してしまった経験はありませんか? それはFOMOの心理を利用したマーケティング戦略かもです。ここでは、FOMOがどのように購買行動を後押しし、実際の施策にどう使われているのかを具体例を交え、ご紹介します。
FOMOマーケティングとは
FOMOマーケティングは、「逃したくない」という感情を刺激して、購買や申込などの行動を促す方法です。人は損をしたくないという気持ちにとても敏感で、その感情が背中を押すきっかけになります。FOMOマーケティングが有効な心理とは、
・限られた機会を逃したくないという損失回避の本能
・他人の行動を基準に判断する社会的証明
・時間や数量に制限があると、判断を急ぎたくなる傾向
実際に、緊急性と特別感を巧みに演出することで、商品やサービスへの関心を一気に高められるとされています。特にネット上では「今ポチらないと、もう手に入らないかも……!」という状況が行動を加速させます。
限定性と緊急性を訴える施策の具体例
FOMOマーケティングの中心にあるのは、限定性と緊急性を感じさせる工夫です。人は、いつでも買えるものよりも「今しか手に入らないもの」に価値を感じる傾向があり具体的には、
ECサイト
商品ページに残り3点、あと2時間でセール終了といった表示を組み込む
宿泊予約サイト
リアルタイムで、いま〇人が閲覧中、あと1部屋と表示して焦りを生む
Amazon
例えばタイムセールではタイマー付きのセールや本日限りなどの文言で即決を促す
アパレル
限定カラーやサイズ展開において今季限定、再入荷なしの記載で購買意欲を引き出す
マーケティング・セールスの売れ筋【書籍】ランキング – Amazon
このような演出がユーザーの決断スピードを高め、より直感的な購買行動を誘導するとされています。FOMOマーケティングは迷わせない仕掛けとしても非常に効果的と言えます。
まとめ:FOMOとどのように向き合うか
SNSやスマホが生活の一部になった今、FOMOを完全になくすのは難しいかもですが、どのように向き合うかによって、日々の過ごし方や心の余裕は大きく変わります。ここでは、これまでの内容をからのFOMOとの適切な距離感についてお伝えします。
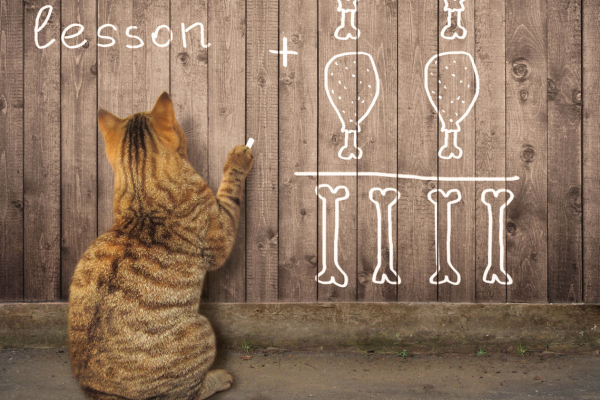
情報ではなく、自分の感覚を優先する
FOMOを手放すために一番大切なのは、自分の価値基準を持つことです。他人の行動や情報に合わせすぎると知らないうちに「置いていかれたくない」という焦りに引っ張られます。ですが自分にとって何が大事かが明確であれば、そういった不安に巻き込まれにくくなります。例えば、
・全部知っている必要はない、と割り切る
・SNSに反応するより、自分の感情に正直になる
・その場にいないことを損ではなく、選択と捉える
FOMOの対極にある考え方「JOMO(Joy of Missing Out)」も参考になり、見逃すことを恐れるのではなく見逃してもいいと受け入れると、その心の余白が、生活全体にゆとりを与えてくれます。
自分のリズムでつながりを選ぶ
FOMOと上手く付き合うには、スマホやSNSとの距離感も見直したいところです。大切なのは、無理に遮断するのではなくスマホやSNSを見ることを、自ら選択する環境にすることです。
・スマホの通知を減らす
・デジタルデトックスを定期的に取り入れる
・SNSを見る時間帯を決める
……などはFOMOに振り回されない工夫です。
表現を少し変えると、情報に追われる側から情報を選ぶ側へ移行する、これがスマホからの情報過多がスタンダードな現代に必要な距離感になるのではと思います。
| 『心理学』人気の本をチェック |
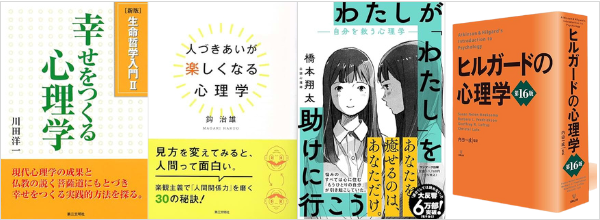 |
| Amazonでチェック |
| 楽天市場でチェック |