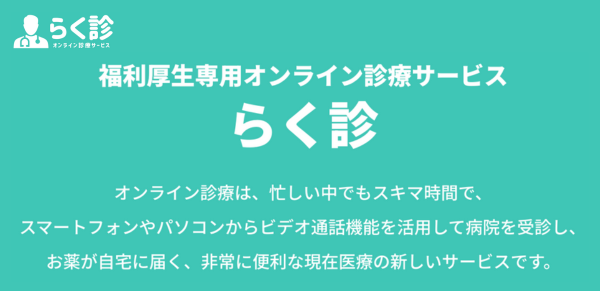| 『自分を変える』人気の本をチェック |
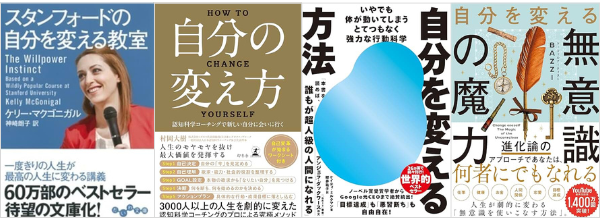 |
| Amazonでチェック |
| 楽天市場でチェック |
「完璧じゃないと意味がない」「もっと頑張らないと」と自分を追い込んでいませんか。完璧主義は一見ストイックで努力家に見える一方で、ストレスや疲労、不安を招く要因にもなりやすいです。
ここでは、心理学や専門的な知見をもとに、自分の完璧主義傾向を見極める方法から、日常で取り入れやすい改善方法までを具体的にご紹介します。

そもそも完璧主義とは? 適応型と不適応型+セルフチェックリスト
完璧主義と聞くと、すべてを完璧にこなす人を想像するかもしれませんが、実はその背景にはさまざまな要因があります。自分がどのタイプの完璧主義に当てはまるのかを知ることで、適切な対処法を見つける手がかりになります。まずは、自分自身の思考や行動パターンを見つめ直してみましょう。

完璧主義には適応型と不適応型がある
完璧主義には、適応型と不適応型の2種類が存在します。適応型の完璧主義は、目標達成への強い意欲や高い自己要求が特徴で、これらが成果を上げる原動力となります。一方、不適応型の完璧主義は、失敗への過度な恐れや自己批判が強く、ストレスや不安を引き起こしやすい傾向があります。
心理学の研究では、適応型の完璧主義者は柔軟な思考を持ち、失敗を成長の機会と捉えることができるとされています。一方、不適応型の完璧主義者は、失敗を許容できず、自己評価が低下しやすいと指摘されています。文章では分かりづらいので、端的にお伝えするとこのようになります。
適応型完璧主義
・高い目標設定
・柔軟な思考
・失敗を学びと捉える
不適応型完璧主義
・過度な自己批判
・失敗への強い恐れ
・柔軟性の欠如
あなたが陥りがちな思考パターンはどれ?セルフチェックリスト
完璧主義の思考パターンは無意識のうちに形成されていることが多く、まずは自覚することが始めの一歩です。自分の傾向を知れば、適切な対処法を選択しやすくなります。心理カウンセリングでは、自己認識が改善の鍵とされ、思考パターンの自覚が行動の変容につながると報告されています。
セルフチェックリスト
① 完璧でなければ意味がない、と感じることが多い
② 失敗を極端に恐れ、挑戦を避ける傾向がある
③ 他人の評価に過敏に反応し、自分を過小評価しがち
④ 細部にこだわりすぎて、全体の進行が遅れる
⑤ 自分にも他人にも厳しく、寛容になれない
これらの項目に多く当てはまる場合、不適応型の完璧主義の傾向があるかもです。自己理解を深めることで、改善へ向かうことができると思います。
完璧主義が引き起こす悩みとその要因
完璧主義は一見ストイックで真面目な性格として評価されがちですが、実は心身のバランスを崩す要因にもなりやすい傾向です。特に「全か無か思考」や「べき思考」といった思考の癖は、慢性的なストレスや疲労を生み出す要因になります。また、完璧主義の根本には幼少期の体験が影響していることもあるので、まずは、その根本的な要因を理解しましょう。

「全か無か思考」「べき思考」が生むストレスの悪循環
完璧主義を持つ人に多い思考の特徴が、「全か無か思考」と「べき思考」です。これは物事を白か黒かで判断し、中間を認めにくい考え方を指します。
・全か無か思考:完璧でなければ失敗と捉える極端な認知。
・べき思考:~すべき、~であるべきと自分に強いルールを課す。
こうした思考が定着すると、以下のような悪循環を引き起こしやすくなります。
・小さな失敗で自己否定が強まり、自信を失う
・過度なストレスにより精神的な疲弊が蓄積
・新しい挑戦を避けるなど、行動が制限される
こうしたストレスは、単なる真面目や努力家といった評価では片づけられない深刻な影響を及ぼすことがあり、早めの対処が必要です。
幼少期の経験や環境が影響していることもある
完璧主義の形成には、子どもの頃の経験や家庭環境が密接に関係している場合があります。特に、以下のような背景が見られることが多いです。
・親や周囲から過剰に期待されて育った
・失敗に対して厳しく叱られることが多かった
・認めてもらうために、完璧でいることを求められた
これらの経験が積み重なると、「期待に応えなければ認められない」「失敗は許されない」といった信念が無意識のうちに根づきます。その結果、大人になっても自己肯定感が低く、常に完璧を追い求める思考につながってしまうことがあります。
ただし、これらの価値観は変えられます。完璧主義に気づいた時点から、少しずつでも柔軟な思考に切り替えていくことが可能です。大切なのは、今までの自分を責めるのではなく、これからの自分に目を向ける姿勢です。
今日からできる完璧主義の和らげ方7選
完璧主義に悩む方は多く、日常生活や仕事においてストレスや疲労を感じているかもですが、少しの意識と行動の変化で、その負担を軽減することが可能です。ここでは、今日から実践できる完璧主義のやわらげ方を7つご紹介します。

① 70点でOKとする
完璧を追求すると、失敗を恐れて行動を起こせなくなることがあります。70点でもOKとすることで、完璧でなくても前進するという行動へのハードルが下がり、継続もしやすくなります。
完璧じゃないと評価されないと思いがちですが、実際には70点でも十分なことが多いです。そのため、完璧を目指したがゆえに時間が無駄になっている可能性もあります。一度試してみましょう。
② あえて『手を抜く・任せる』を練習する
完璧主義の人は、すべてを自分で完璧にこなそうと抱え込みがちですが、それがストレスや燃え尽きの要因になります。意識的に手を抜いたり、他人に任せることで、自分の負担を減らせば心に余裕が生まれます。結果、全体の効率も向上する可能性もあります。
完璧を目指すと、仕事が進まないし、いつまで経っても終わらないことが多いです。完璧を目指すよりもスピード感をもって70点で仕上げてブラッシュアップするのが仕事の出来る人の進め方です。
③ 結果ではなく過程に目を向ける
完璧主義の人は、成果にこだわりすぎて過程を評価しない傾向があります。結果だけでなく、過程や努力に目を向けることで、自己評価が高まり、完璧主義のプレッシャーが軽減されます。
また、過程を重視することで失敗を恐れずに挑戦できるようになります。もう一つ見方を変えると、完璧主義は「失敗=終わり」と考えがちですが、失敗は成長する機会です。
④ 自分に優しするセルフトーク法
完璧主義をやわらげるためには、自分自身に対する思いやりのある言葉が効果的です。これは「セルフ・コンパッション」とも呼ばれ、自己批判を減らし、ストレスを軽減する助けになります。
具体的には、失敗したときに「誰にでもミスはある」と自分に語りかけることで、自己肯定感を保つことができます。この方法は、困難な状況でも前向きに対処する力を養います。

⑤ タイムリミット思考を取り入れる
完璧を求めるあまり、作業に過度な時間を費やすことがあります。これを防ぐために、あらかじめ時間の制限を設ける『タイムリミット思考』が有効です。
例えば、プレゼン資料の作成に2時間と決め、その時間内で形にします。この方法により、効率的に作業を進めることができ、過度な完璧主義から解放されます。
⑥ とにかく始める
完璧を目指すあまり、行動を起こせないことがあります。このような場合、とにかく始めるという考え方が役立ちます。
例えば、ブログ記事を書く際に、完璧な内容ではなく、まずは書き始めるようにします。とにかく始めてしまえば結構、夢中になってしまうものです。結果として成果を得やすくなります。
⑦ 『できていること』に意識を向け記録もする
完璧主義の方は、自分の欠点や不足に目が向きがちです。これを改善するために、日々の「できたこと」を記録する習慣を持つことが効果的です。
例えば、日記やメモにその日の達成事項を書き出すことで、自分の成長や努力を可視化できます。この習慣は、自己肯定感を高め、前向きな思考を促進します。
完璧主義を活用し、ネガティブ要因ともバランスする方法
完璧主義は、細部へのこだわりや高い目標設定など、仕事や学習において強みとなる側面があります。ですが、過度な完璧主義は、ストレスや燃え尽き症候群の要因にもなり得ます。ここでは、完璧主義のポジティブやメリットと言える面を活用しつつ、ストレスなどのネガティブ要因ともバランスを取るための考え方や実践方法をご紹介します。
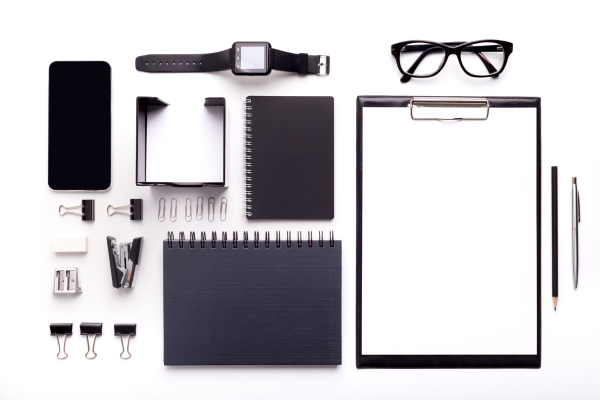
適度主義で力の入れどころを見極める
完璧主義の長所を活かすためには、適度主義の考え方が有効で、すべてを完璧にこなすのではなく、重要な部分に集中して取り組むというアプローチです。この方法により、エネルギーを効率的に使い、成果を最大化することが可能になります。
具体的な実践方法
・タスクを重要度と緊急度で分類し、優先順位を明確にする
・完璧を求めるべき部分と、妥協しても問題ない部分を見極める
・完璧でなくても良い、と自分に許可を与える
このように、力の入れどころを見極めることで、無駄なストレスを減らし、持続可能なパフォーマンスを維持することができます。
仕事や人間関係での活かし方を考える
完璧主義の特性は、仕事や人間関係においても活かすことができます。例えば、仕事での細部へのこだわりや高い基準は、品質の高い成果物を生み出す原動力となりますし、責任感の強さや計画性は、社内での人間関係において信頼を築く要素となります。ただし、注意点もあります。
・他人にも自分と同じ高い基準を求めすぎない
・失敗やミスを過度に恐れず、柔軟な対応を心がける
・自己評価を厳しくしすぎず、達成したことを認める
これらの点を意識することで、完璧主義の特性をポジティブに活かしつつ、ネガティブ要因を打ち消していくことができると思います。
完璧主義の改善アプローチ方法を専門家から学ぶ
完璧主義に悩む方は、自分の力だけでその思考パターンを変えるのが難しいと感じることもあるかもですが、専門家の手を借りることで、新たな視点や対処法を得られる可能性があります。ここでは、認知行動療法や心理カウンセリングなど、専門的なサポートについてご紹介します。

認知行動療法(CBT)で考え方の癖を整える
認知行動療法(CBT)は、思考の歪みに自分で気づき、それを修正する手法であるため、完璧主義的な思考パターンを見直すのに有効な方法の一つです。例えば、「全か無か思考」や「べき思考」といった極端な考え方を柔軟に変えていくことを目指します
・自分の思考パターンを記録し、認識する
・その思考が現実的かどうかを検討する
・よりバランスの取れた考え方に置き換える
これにより、完璧でなければならないという重圧から解放され、柔軟な思考が可能になります。
心理カウンセリングや医師によるサポートの選択肢
専門家が個々の背景や状況に応じたアプローチを提供できることから、心理カウンセリングや医師のサポートを受けることは、完璧主義の改善に役立つ選択です。例えば、幼少期の経験や家庭環境が完璧主義に影響している場合、それを理解し適切に対処することが求められます。
カウンセリングのサポート例
・自己理解を深めるための対話
・ストレスや不安への対処法の習得
・行動パターンの見直しと改善
また、必要に応じて医師の診断や治療を受けることで、心身の健康を保ちながら完璧主義と向き合うことができます。
まとめ:『完璧じゃなくていい』とするには?
完璧主義は決して悪いものではなく、真面目さや責任感の強さの裏返しでもあります。ただし、その傾向が強くなりすぎると、自分を追い込み、人間関係や生活全体にも影響が出てしまうこともあります。この記事では、完璧主義とうまく付き合うための考え方や具体的な対処法をご紹介しました。簡易的ですが、まとめです。

完璧主義をやめるのではなく、付き合い方を見直す
完璧を目指す性質は、その人の価値観や性格に深く根付いていることが多いため、無理に手放そうとすると逆にストレスになるため、完璧主義を完全に『辞める』のではなく『どう付き合うか』を意識した方が良いです。表現を変えるなら、距離感を見直すとも言い換えることができます。
具体的なアプローチ例
・完璧じゃなくていい、と自分に言い聞かせる習慣を持つ
・全体のバランスを見て力を抜くポイントを作る
・他人にも、完璧を求めすぎない
完璧主義は、方向を少し変えるだけで丁寧さ、責任感として活かせる特性です。否定するのではなく、扱い方次第で良い方向に十分すぎるほど活用できる要因になります。
あなたのペースで、少しずつ変わっていける
急激な変化は心理的な負担が大きく、かえって逆戻りしてしまうリスクが高いため、完璧主義の見直しは一気に変わるのではなく、少しずつ慣れていくことがおすすめです。
具体的なアプローチ例
・毎日ひとつだけ、70点でOKなことを決めてみる
・できたことに注目して日記やメモに書き出す
・できなかったことよりも、できたことに目を向ける
小さな一歩でも積み重ねていけば、無理なく自分の考え方や行動を変えていくことができます。「完璧」よりも「続けられる」を意識することで、もっと心地よい日常に近づけるはずです。
| 『自分を変える』人気の本をチェック |
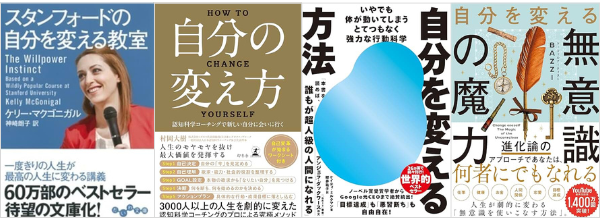 |
| Amazonでチェック |
| 楽天市場でチェック |