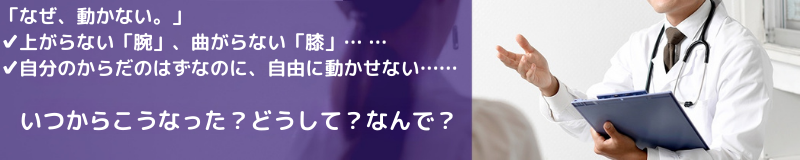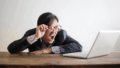自己肯定感と自己効力感、それぞれ心のどのような働きなのか、またどのような場面で活かせるのかを、この記事でお伝えします。知ることによって、仕事や人間関係、さらには子育てなどにも活用することもできるかと。
| 『自己効力感』で人気の本をチェック | 『自己肯定感』で人気の本をチェック |
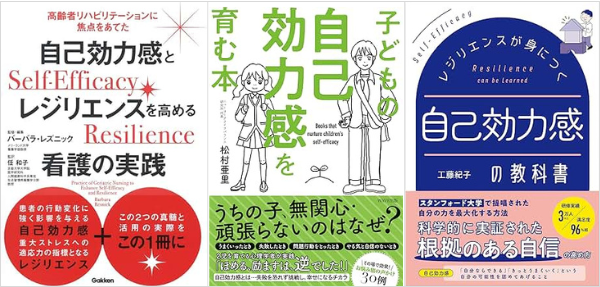 |
 |
| 楽天市場でチェック | 楽天市場でチェック |
| Amazonでチェック | Amazonでチェック |
場面ごとの使い分けや高め方、そして両者が支え合う仕組みなど、もし今「もっと自信を持って前に進みたい」と感じているなら、読み進めていただければと思います。
自己効力感と自己肯定感の違い
ここでは、自己効力感と自己肯定感の違い、どのように使い分けると良いのかをお伝えします。

自己効力感は信念・自己肯定感は感情
自己効力感は「自分ならできる」と信じる力、自己肯定感は「自分には価値がある」と感じる力です。この2つは一見似ていますが、実は働く領域が違います。
自己効力感は能力に対する自信であり、物事に取り組むときの行動を支える信念です。たとえば、難しい仕事を前にしたときに「自分ならやれる」と思えるかどうかが、それにあたります。
一方の自己肯定感は、できるできないに関係なく、自分の存在そのものに対して価値を感じられる感情です。何かに失敗しても、それでも自分には意味があると思えるかどうかがポイントです。
自己効力感:目標達成のために、自分には力があると信じる感覚(信念)
自己肯定感:できるできない無関係に、ありのままの自分を受け入れる感覚(感情)
ケース別の使い分け(例:就職活動・子育て・学習)
状況によって、自己効力感と自己肯定感のどちらを重視するかは変わってきます。その理由は、求められる力の種類が場面ごとに異なるからです。以下のように、目的に応じて意識するポイントを切り分けると効果的です。
就職活動や転職活動の場面では
→ 自己効力感です。「自分にはこの仕事ができる」という明確な根拠やエピソードが、自信として表れ、説得力を持たせます。
子育てや教育の場面では
→ まず育てたいのは自己肯定感です。「君はそのままで大切な存在だよ」と伝えることが将来の挑戦を支える土台になります。
資格取得やスキル学習の場面では
→ 自己効力感です。「やれば自分にもできる」と信じられるかどうかが、継続力と学習成果に直結します。
このように、「何を目的にしているか」によって育てるべき自己感を使い分けることで、より確かな成果を得やすくなります。
| 『自己効力感』で人気の本をチェック | 『自己肯定感』で人気の本をチェック |
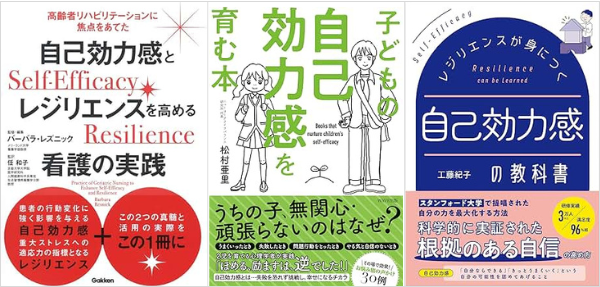 |
 |
| 楽天市場でチェック | 楽天市場でチェック |
| Amazonでチェック | Amazonでチェック |
そもそも自己効力感とは
「自分ならできる」という気持ちが挑戦への第一歩になることって多いです。このできる気がする感覚こそが、自己効力感です。ただのポジティブではなく心理学に基づいた理論が背景にあるので、ここでは、自己効力感のルーツから、実際の具体的な効果をお伝えします。

心理学的な定義
自己効力感は気分や性格ではなく、ある行動に対して「自分ならやりきれる」と思えるかどうかです。例えば新しい仕事を任されたとき「自分ならなんとかできるはず」と思えるか、「無理かも」と感じるか。その差が、自己効力感の有無に関係しています。表現を変えると、自己効力感は「自分に能力があると信じられている状態」であり、
・自分の行動に対する前向きな認知
・何かに挑戦するときの心理的な土台
・結果よりも、やれるかどうかの判断材料
として働くものです。
心理学者アルバート・バンデューラによる自己効力感の理論
自己効力感の概念を提唱したのは、カナダの心理学者アルバート・バンデューラで彼は「人は、外からの影響だけでなく、自分の信念によって行動が変わる」と考えました。その中心にあるのが自己効力感で、人が行動を起こすかどうか、やり抜けるかどうかに大きく関わるとしています。尚、バンデューラの理論では、自己効力感は次の4つの経験から育まれるとされます。
・成功体験(遂行達成):やり遂げた経験は自信につながる
・他者の成功を見る(代理経験):似た立場の人の成功を見て「自分もできるかも」と思える
・励ましの言葉(言語的説得):周囲の応援が背中を押してくれる
・心身のコンディション(情動的喚起):リラックスした状態のほうが「できる」と感じやすい
この理論は、教育・ビジネス・医療などあらゆる現場で応用されています。
行動からの成果に影響する高い自己効力感の効果
自己効力感が高い人は、チャレンジに前向きになりやすく、結果として成果にもつながりやすくなります。なぜなら、自分ならできると思えることで、不安よりも行動が先行されるためです。反対に、自己効力感が低いと「どうせ無理だろう」からの、最初の一歩すら踏み出せないこともあります。
自己効力感が高いことによる効果
・チャレンジ精神が高まり、行動量が増える
・失敗から立ち直る力が強くなる
・やる気が長く続き、努力を継続しやすくなる
このように、自己効力感はただの気持ちの問題ではなく、行動の質を変え、結果を左右する大きな要素と言えます。
そもそも自己肯定感とは
自分に自信が持てない、つい他人と比べて落ち込んでしまう、そのような時に深く関わっているのが、自己肯定感です。ここでは、自己肯定感の基本的な意味から、特徴、そして心理学的な背景について丁寧に整理していきます。

『ありのままの自分』を受け入れる感情が自己肯定感
できるできない無関係に自分の存在に価値があると信じられるかどうか、これが自己肯定感の高い低いの分水嶺になります。何か特別な成果を上げたわけじゃなくても「自分はこれでいい」と思える、その感覚がベースになります。
自己肯定感の具体的な感覚の例
・他人と比較せず、自分の価値を認めること
・自分の長所も短所も、ひっくるめて受け止めること
・変わろうとする意志の前に、自分を受け入れる余裕を持つこと
この感情が育っていれば、多少の失敗があっても大丈夫と思える土台になります。
自己肯定感が高い人と低い人の簡易比較
自己肯定感が高い人は安定して前向きに行動でき、低い人は他人の評価に左右されがちです。
自己肯定感が高い人の特徴(一例)
・自分の得意なことをしっかり理解している
・評価よりも「自分がどう思うか」を大切にしている
・失敗しても引きずらず、前を向くのが早い
自己肯定感が低い人の特徴(一例)
・他人と比べて落ち込むことが多い
・自分の価値を他人の評価で決めがち
・自分の短所ばかりに目がいってしまう
自己肯定感が低いと、周囲の期待に応えようと無理をしがちになり、結果的に自分を消耗させてしまう懸念があります。自己肯定感が高いからの自分の内側から湧く「これでいい」という感覚が、行動や判断の安定を支えてくれます。
発達心理学での自己肯定感とは『心の土台』
発達心理学では、自己肯定感は人生を通じて形成される心の土台として重視されています。この感覚は、生まれつき備わっているものではなく、育っていく過程で徐々に形作られていきます。特に、幼少期から思春期にかけての家庭環境や大人との関わり方が大きく影響します。たとえば、
・親から「あなたのままでいいよ」と言われた経験
・小さな成功体験を積み重ねたこと
・失敗しても見守ってくれる存在がいたこと
こういった経験が、自己肯定感の根っこを育ててくれます。ただし、大人になってからでも自己肯定感は十分育てることができるとされています。心理学的にも自己受容の力は、自己実現や長期的なメンタル安定に欠かせない要素とされています。
| 『自己効力感』で人気の本をチェック | 『自己肯定感』で人気の本をチェック |
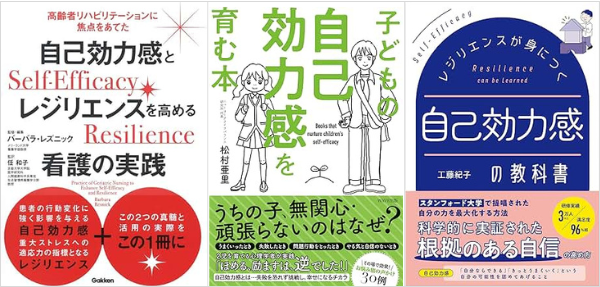 |
 |
| 楽天市場でチェック | 楽天市場でチェック |
| Amazonでチェック | Amazonでチェック |
自己肯定感と自己効力感の相互作用
自己肯定感と自己効力感は、まったく別物ではなく、お互いを支え合ったり、補ったりする関係でもありますので、ここでは両者がどのような関連性を持っているのか、具体的にお伝えします。

自己肯定感が自己効力感に与える影響
自己肯定感は心の土台でもあるので、自己肯定感が高い人の特徴でもある、
・自分の存在に価値があると信じられる
・他人の評価に過剰に振り回されない
・失敗を恐れず、やってみようと思える
このような状態にあると、自然と「自分にもできるはず」という自己効力感が生まれやすくなるんです。土台となる自己肯定感が安定することで、行動する力にもつながっていきます。
自己効力感が自己肯定感を補完する場面
自己効力感は自己肯定感が揺らぎ、自信を失いかけたとき根拠ある支えになります。例えば「自分って何もできてないな」と虚無感があるような時に、過去に自分が頑張ってやり遂げた経験や人に頼られた体験から頭を切り替えて「いや、自分にはちゃんとできたこともある」と思えるかどうか。
・成功体験を思い出せる(些細なことでOK)
・誰かの言葉で自信を取り戻せたことがある
・他人の成功を見て、自分にも可能性を感じたことがある
こうした体験があると、自己肯定感が一時的に下がったときでも、自分を立て直すきっかけになります。つまり、自己効力感は行動の記憶を通して自己肯定感を支える役割も担っています。
自己効力感と自己肯定感をバランスさせる
・自己肯定感が高く、自己効力感が低いと「自分は価値ある人間だけど、何もできないかも」等
・自己肯定感が低く、自己効力感が高いと「できるけど、自分に価値があるとは思えない」等
どちらも行動や好ましい成果には結びつき難いことが明確なのではないでしょうか。そこで、この両者のランス取りためには、例えばこのような習慣がおすすめです。
・毎日の小さな達成を記録する(行動の自信につながる)
・失敗しても「行動した自分」を肯定してあげる
・他人と比べず「昨日の自分」と比べる習慣をつける
このようなことを積み重ねていくと、自己肯定感という土台と、自己効力感という前に進む力を一緒に育てていくことができます。
自己効力感を高める具体的な方法4選

このテーマだけで1つ記事を書くことができてしまいそうなので、ここでは簡略的に自己効力感を高める実践的なアプローチ4つをお伝えします。
① 成功体験を積み重ねる
小さな成功を繰り返すことは自己効力感を高める最も有効な手段です。
② ロールモデルによる代理経験
代理経験とはバンデューラの理論でも自己効力感を育てる重要な手段のひとつであり、特に自分と近い立場の人が何かを成し遂げた姿を見ると、自分にもできるかもと思いやすくなります。
③ 周囲による言語的説得
特に、信頼している人からのポジティブな声かけは、自分の中の「できるかも」を後押しします。例えば「この前のプレゼン、分かりやすかったよ」などです。素直に受け取ってりましょう。
④ 心身をマネジメントする
自己効力感は気分や体調と連動してしまうので、不安が過剰だったり、疲れているときは低迷することが多いです。手っ取り早い解決方法は寝る時間を増やしましょう。
自己肯定感を高める具体的な習慣と考え方3選

自己肯定感は、誰でも日常の積み重ねで日々の考え方や習慣を少しずつ整えることができます。ここでは、そのためにできる具体的な方法を紹介します。
① 否定的な自己評価をしない
失敗やうまくいかない経験があるのは誰でも同じなので、物事の受け取り方や解釈を変えましょう。「できなかったこと」ではなく「できたこと」に意識を向ける等
② 自分の価値を言語化する
変化や成長に目を向けることで自分の価値を見つめ直すことができるものなので、例えば昔の自分と比べて成長したことや、周囲の人からよく言われる自分の強みを箇条書きにしてみましょう。
③ 感謝されたら素直に受け取る
自己肯定感が低い時は他人から褒められても「そんなことない」とつい否定してしまいがちですが、跳ね返してしまうと、自分の中にある自己肯定感の芽が育たなくなってしまいます。
実は深掘りしたことがあるので、その時の記事がこちらです。

まとめ:自己効力感と自己肯定感
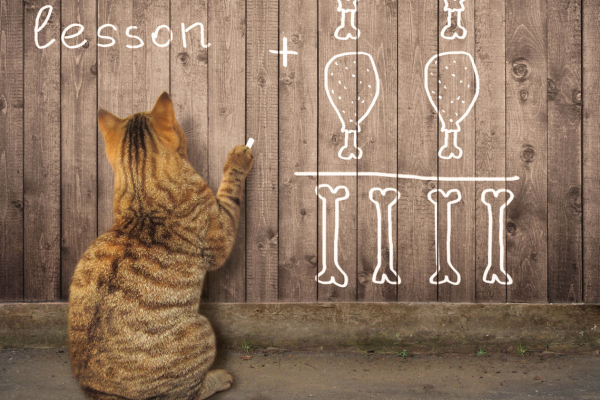
・自己効力感は「できる」と信じる力、自己肯定感は「価値がある」と認める感情であり、それぞれ異なる心の働きを担っています。
・自己効力感は成功体験や他人の成功を見ることで育ち、行動力や継続力の強化につながります。
・自己肯定感は自分の存在そのものを受け入れる感覚で、失敗しても自分を否定せずにいられる心の土台になります。
・両者は相互に影響し合い、片方だけが高くてもバランスを欠くため、意識して両方を整えることが大切です。
・小さな成功の積み重ねや、肯定的な言葉を受け入れる習慣を通じて、自己効力感と自己肯定感は誰でも育てることができます。
| 『自己効力感』で人気の本をチェック | 『自己肯定感』で人気の本をチェック |
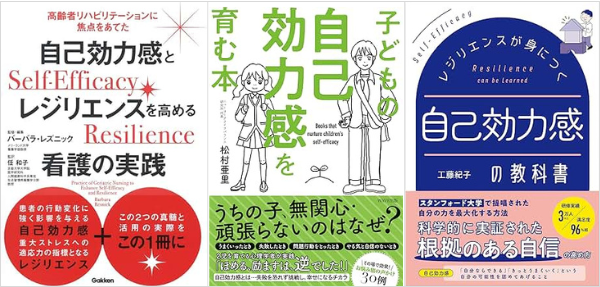 |
 |
| 楽天市場でチェック | 楽天市場でチェック |
| Amazonでチェック | Amazonでチェック |