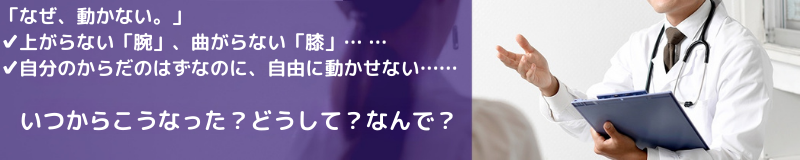| 『確率思考の戦略論』をチェック |
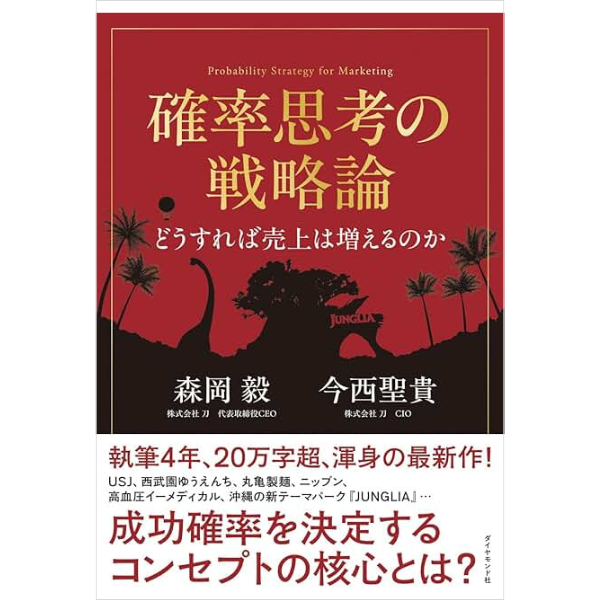 |
| Amazonでチェック |
| 楽天市場でチェック |
「確率思考の戦略論 どうすれば売上は増えるのか」森岡毅 (著)、今西聖貴 (著)の書籍を要約し、記事にしました。マーケティングはセンスではなく確率で決まる、もしこの考え方が本当なら、あなたのビジネスの売上を伸ばす方法も明確になるはずです。
本記事では、USJのV字回復を実現した森岡毅氏が提唱する「確率思考の戦略論」を要約し、その本質をわかりやすく解説します。
プレファレンス(好意度)を高めることの重要性、ゴールから逆算する思考法、データを活用した戦略設計など、すぐに実践できるポイントを厳選しました。売上を伸ばす「確率」を上げるための鍵を知ることができます。
確率思考の戦略論とは?本の概要
”マーケティングやビジネス戦略の成功は「確率」によって決まる”——この考え方を徹底的に解説したのが『確率思考の戦略論』です。本書では、USJをV字回復させたマーケティング戦略や、データを活用したビジネスの意思決定手法が紹介されています。「マーケティングを数値で考える」という視点を身につけることで、売上向上に直結する戦略を理解できます。では、具体的にどんな内容が学べるのでしょうか?

著者と書籍の基本情報
本書は、USJの再生を成功させたマーケターと、数理モデルを専門とする経済学者による共著。マーケティングをデータと確率の視点から解説した一冊です。ビジネスの意思決定には経験則ではなく、確率やデータ分析が必要であることを伝えます。
本書の著者は、USJのマーケティング戦略を手がけた森岡毅氏と、数理経済学者の今西聖貴氏。森岡氏は、USJのV字回復を実現したマーケターであり、消費者の「プレファレンス(好意度)」を高める戦略を数値的に設計しました。一方、今西氏は数理経済学を専門とし、確率モデルを活用したビジネス戦略を研究しています。両者の知見が融合した本書は、直感ではなくデータで考えるマーケティングの重要性を強調しています。
この本で学べること
『確率思考の戦略論』は、消費者のプレファレンス(好意度)を高める方法や、確率を活用したマーケティング戦略の立て方を学べる本です。売上向上のカギは「消費者の選択確率を上げること」であり、そのための具体的な手法が紹介されています。本書では、マーケティングにおいて「プレファレンス(好意度)」が売上に与える影響を徹底的に解説しています。

例えば、USJの「ハリーポッター・エリア」の成功は、来場者のプレファレンスを高めた結果として説明されます。また、ゴールから逆算する戦略思考や、データドリブンな意思決定の重要性が、数式や実例を交えて解説されています。これにより、マーケティング施策を確率の最適化という視点で捉えられるようになります。
なぜ「確率思考」がマーケティングで重要なのか?
マーケティングの成功は「センス」や「運」ではなく、「確率」によって決まると聞いたら、驚く人もいるかもしれません。しかし、「確率思考の戦略論」では、売上を伸ばすためには消費者が自社の商品を選ぶ確率を高めることが重要だと説明しています。では、なぜマーケティングが確率で決まり、その確率を高めるために何が必要なのかを解説していきます。
マーケティングは確率で決まるマーケティングの成否は「確率」で決まる
多くの企業は「売上を伸ばすにはどうすればよいか?」という課題に直面していますが、本書の結論は明快です。「売れる確率を上げることが売上増加につながる」 という考え方です。
どんなに良い商品やサービスでも、消費者が購入を決める確率が低ければ売上は伸びません。例えば、100万人の市場で、購入確率が0.1%のA社の商品と、0.5%のB社の商品があるとします。B社の方が売れる確率が高いため、同じ市場規模でも売上は5倍になります。
このように、確率を制御することがマーケティングの本質なのです。確率を上げるためには、消費者が商品を「欲しい」と思う要因を強化することが不可欠です。その鍵を握るのが「プレファレンス(好意度)」です。

好意度が売上を左右し好意度が高いほど商品は選ばれやすい
プレファレンス(好意度)を簡単に言えば、「この商品が好き」「このブランドなら間違いない」と思ってもらえるかどうかが、市場での競争力を左右します。人は購入時に「選択肢の中から最も好ましいものを選ぶ」傾向があります。
例えば、コーヒーを買うときに「スターバックス」「ドトール」「コンビニコーヒー」の選択があるとします。このとき「スタバが好き」と思っている人は、高確率でスターバックスを選ぶでしょう。これは「プレファレンスが高いブランドほど、選ばれる確率が上がる」ことを示しています。
プレファレンスを高めるには?
プレファレンスを向上させるためには、
・ブランドの認知度を高める(多くの人に知ってもらう)
・一貫したブランド体験を提供する(期待を裏切らない)
・感情的なつながりを作る(「好き」と思ってもらう)
このプレファレンスを向上させることで、実際にUSJは来場者数を劇的に増加させました。この戦略については、次の見出しで詳しく解説します。
| 『確率思考の戦略論』をチェック |
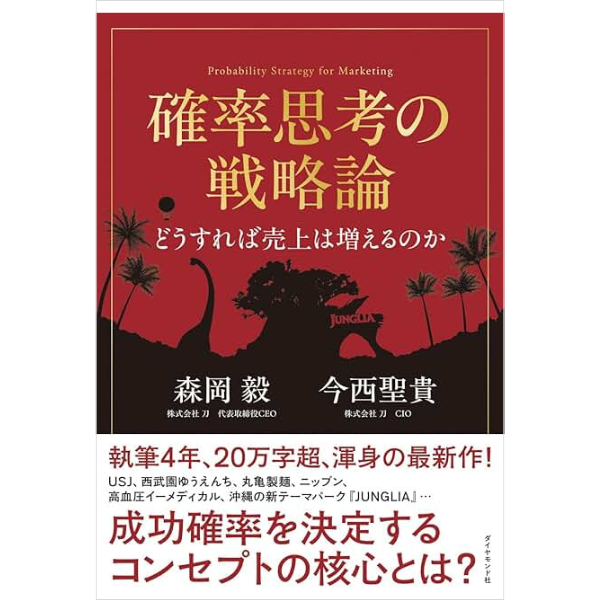 |
| Amazonでチェック |
| 楽天市場でチェック |
売上を伸ばすための戦略【成功する3つの要素】
マーケティングの成功は偶然ではなく、確率をコントロールする戦略的なアプローチによって決まります。本書では、売上を伸ばすために必要な3つの要素として、
①プレファレンスを高める
②ゴールから逆算する
③データドリブンな意思決定を行う
というポイントを挙げています。では、どのように実践すれば効果的なのかを見ていきましょう。
① プレファレンスを高める
・ブランドの認知度を上げる(広告・SNS・口コミ)
・一貫したブランド体験を提供する(顧客の期待を裏切らない)
・感情的なつながりを作る(ブランドストーリーの活用)
例えば、USJは「ハリーポッターエリアの世界観を徹底的に作り込む」ことで、顧客のプレファレンスを高め、リピーターを増やすことに成功しました。
② ゴールから逆算する
ゴールが明確でないと、戦略の方向性がブレてしまいます。たとえば、「年間売上100億円を達成する」という目標を設定した場合、そこに到達するために「どの市場を狙うのか?」「どの施策が必要か?」と具体的な戦略を導き出せます。
・最終ゴールを設定する(売上100億円、顧客数○万人など)
・ゴール達成に必要なKPIを決める(客単価、リピート率など)
・具体的な施策を組み立てる(プロモーション、商品改善など)
例えば、西武園ゆうえんちは「エンタメの質を上げる」ことをゴールに設定し、価格設定や演出を全て逆算して考えた結果、入場者数を大幅に増やしました。
③ データドリブンな意思決定を行う
売上を伸ばすための施策を考える際「過去の経験」や「なんとなくの直感」に頼ってしまいがちですが、確実に成果を出すためにはデータを活用することが不可欠です。マーケティング施策の効果を最大化するためには、どの施策が成功しやすいかを客観的に判断する必要があります。
例えば、「この広告はどれくらいのコンバージョン率があるのか?」「どのターゲット層が最も反応しているのか?」という分析を行うことで、より高確率で成功する施策を選べます。
・正しい指標を設定する(売上、CVR、LTVなど)
・データを可視化する(ダッシュボードや分析ツールの活用)
・仮説検証を繰り返す(A/Bテストや顧客分析)
たとえば、丸亀製麺は「どの時間帯にどんなメニューが売れるか?」をデータで分析し、それに基づいた販促施策を実施することで売上を大きく伸ばしました。

確率思考の戦略論の実践例【成功事例3選】
『確率思考の戦略論』の理論は、単なる理論ではなく、実際のビジネスの現場で活用されています。本書では、USJ・西武園ゆうえんち・丸亀製麺 の3つの事例を通じて、どのように「確率思考」をマーケティング戦略に落とし込み、成果を上げたのかが解説されています。
「消費者に選ばれる確率を上げる」という視点を持つことで、どのようなビジネスにも応用可能な考え方が見えてきます。では、それぞれの成功事例を詳しく見ていきましょう。

事例①USJ:テーマパーク復活の裏にあった確率思考
USJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)は、かつて「ディズニーには勝てない」と言われ、経営難に陥っていましたが「消費者に選ばれる確率」を高める戦略を徹底したことで、驚異的なV字回復を果たしました。
USJは、「とにかく面白い体験を提供する」 という方針から、 特定のターゲット(20〜30代の若者層)に響く施策を実施しました。ディズニーが家族向けのイメージを強く持つ中、USJは「映画やゲームの世界をリアルに楽しめる場」としての差別化を徹底しました。具体的な施策の成功例は、
・ハリー・ポッターエリアの世界観作り → ブランドへの没入感が向上しプレファレンス強化
・ゾンビナイトなどの季節イベント → SNSで拡散されやすく若年層の集客に成功
・フライング・ダイナソーなどの絶叫系アトラクションの強化 → ターゲット層の満足度アップ
ターゲットにどのように選ばれるか?を逆算し、プレファレンスを高める施策を実行したことで、業績回復に成功しました。
事例②西武園ゆうえんち:「昭和レトロ戦略」の勝因
西武園ゆうえんちは、USJやディズニーのような規模の大きなアトラクションではなく、「昭和レトロ」という独自のテーマを打ち出すことで再生を果たしました。テーマパーク市場は、ディズニーやUSJのような巨大な施設が強い影響力を持っています。そこで西武園ゆうえんちは、「他のテーマパークと同じ土俵で戦わない」 という戦略を選びました。具体的な施策の成功例は、
・夕日の丘商店街など、昭和の街並みを忠実に再現 → 昔を懐かしむ層に強く響いた
・スタッフが役者のように振る舞う → 「非日常の体験」として価値を提供
・デジタル技術を排し、完全アナログ体験 → 競合にはない独自性を確立
このように、競争の激しい市場での勝ち方として「他と違う価値を提供する」という確率思考を活用した結果、西武園ゆうえんちは見事に再生を果たしました。
事例③丸亀製麺:単なるうどんチェーンが熱狂を生んだ理由
丸亀製麺は、ただのうどんチェーンではなく「できたて」「手作り感」を前面に打ち出す戦略を採用し、競争の激しい外食産業の中で強いブランドを確立しました。外食チェーンの多くは「安さ」や「スピード」で競争します。しかし、丸亀製麺は 「手作り感が伝わるプロセス」を体験させることで、顧客の満足度を高める ことに注力しました。具体的な施策の成功例は、
・店内で粉からうどんを打つライブ感 → 目の前で作られることで「できたて」の価値を実感
・トッピングの自由度を高める → 顧客が自分好みのうどんを作れる楽しさを提供
・従業員が職人な接客をする → チェーン店ではなく、本物のうどん屋の印象を与える
これにより、「うどんを食べる」ではなく「うどんを楽しむ」 という体験価値が生まれ、結果として競争優位性が確立されました。
まとめ:USJ、西武園ゆうえんち、丸亀製麺の共通点
これらの成功事例に共通するのは、確率思考に基づいた戦略が採用されていることです。

・USJ は「ターゲットに徹底的に刺さるコンテンツ」を作り、選ばれる確率を上げた
・西武園ゆうえんち は「独自の体験価値を提供」し、競争を回避して成功した
・丸亀製麺 は「うどんを作るプロセス」を前面に出すことで、消費者のプレファレンスを高めた
「どうすれば売上が伸びるのか?」という問いに対する答えは、確率思考による戦略的なアプローチにあることが、これらの事例からも明らかです。
まとめ:確率思考の戦略論 要約
・マーケティングの成功は偶然ではなく、消費者が商品を選ぶ確率を高める戦略が鍵です。
・プレファレンス(好意度)を向上させ競争優位を確立できれば、売上を伸ばせます。
・成功する企業はゴールから逆算し、データを活用した意思決定を徹底しています。
・USJ、西武園ゆうえんち、丸亀製麺は、確率思考の成功はマーケティング戦略の活用による。
・マーケティング施策最適化は確率の操作であり、直感ではなくデータに基づいた戦略が不可欠。
| 『確率思考の戦略論』をチェック |
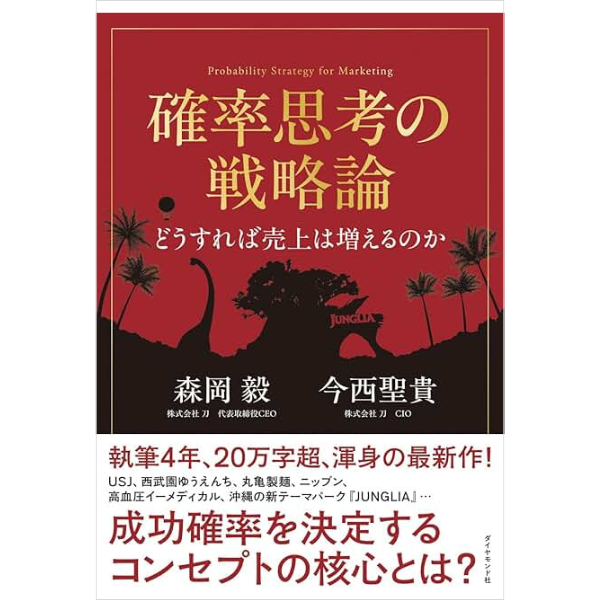 |
| Amazonでチェック |
| 楽天市場でチェック |